オッド・メドロア
Voice:氷炎
旧暦(高度文明期)
享年:33歳
属性:炎・水属性
出身:セントラル(孤児)
新暦(人類滅亡後)
KEEPER=PISCES/魚座の守護者
役割:C-GE:支援型戦闘機巧
不穏な逸材 / 二魔を喰む遺狐
彼の現在のコードネームはKEEPER=PISCES。
『魚座』の名をその身に冠する中距離戦闘型アンドロイドで、躯体には戦闘用の仕掛けが多数施されている。常に火水のエネルギーが効率よく集まる特殊仕様を保有しており、強力な魔法戦闘も可能である旨、整備部門から報告が上がっているが、なぜだか彼は魔の力に頼りたがらない。自身にそんな制約を課す彼は、それでも決して仲間には迷惑をかけまいと、同部門所属のLEOとの体術訓練や、DAME=GEMINIとの武器改良に日々全力を注いでおり、強力な戦闘支援役として社会貢献を果たしている。
SAGITTARIUSには少々苦手意識があるようで、彼女が近くに居るとなぜだか常に気まずそうにしている。一方、役立たずと揶揄され続ける“ロールレス”にはかなりの愛着があるらしく、LEOになんだかんだと文句を言われながらも、よく世話を焼いているようだ。
そんな彼のオリジナルの魂の名は、オッド・メドロア。
魔の力を極度に嫌う少々偏屈な努力家の、壮絶な過去の軌跡を追ってみることにしよう。
キャラクターボイス
『人の役に立ちたいんだ』
『勘弁してくださいよ・・・勘弁してくださいよ・・・!!
・・・・・・絶対に・・・死なせるもんか!!!』
STORY
▼EP7:『オッド・メドロアの軌跡』
彼は戦争孤児だ。セントラルと北地、東地の三国の国境線が交わる場所に近い、北地のとある領地で保護され、紆余曲折の末にセントラルの養護施設に引き取られた為、詳しい出自については不明だが、火と水の二属性を扱える事実から、おそらく北国と南国のハーフと推定されている。
後のイヴ・マイヤと同じく、多属性持ちの稀少な魔導師、要は『逸材』としてセントラルが獲得した人材だったわけなのだが、人類暦2081年「旧型機巧台頭によるアストラルフレア枯渇の環境問題」以降、セントラル政府が「人類の魔法使用」に関しての方針を転換したことにより、彼は約束されていたはずの華々しい出世の道を絶たれて、一気に「厄介者」として扱われるようになってしまった。
ただ、本人はそういった事情をあまり気にしていない様子で、政府方針が転換された後はアダムが開発した「アストラルフレア(魔素)制限装置」を愛用し、自身の力をきっちりと制御して晩年まで軍での仕事を続けている。時にはその努力すら認められず、馬鹿にされることもあったそうだが、彼はそういった周囲の人々の変化にもあまり動じなかったという。
「人の役に立ちたいんだ」
経緯はどうあれ、物乞いで腹を満たし、時には泥水すら啜った孤児時代を思えば、セントラルに引き取られてからの生活は楽園だった。自身の立場が少々危うくなったとして、変わらずに接してくれる人もたくさんいる。彼は、決して、人を恨まなかった。
▼ODD:EP7-1(2073年):『不穏な逸材』
軍幹部の男「ヌル大将閣下へ定例報告申し上げます。
北東地との国境付近で保護された例の孤児についてなのですが・・・」
ヌル「あぁ、報告ご苦労。例の多属性持ちの雄ガキか。結局、火と水の二属性?」
軍幹部の男「はい。間違いありません。風と地については適性がないとのことです。
力の程度についても全ては将軍の想定どおりでした。
通常の人間の約3~4倍ほどのアストラルフレアを体内に取り込んでの各種戦闘が可能との報告が上がってきております。
また、水の才についてなのですが、あの冥脈神殿の神官長クラスの高位魔法と類似する特殊な波長を含んでいる、とのことでして・・・」
ヌル「わーぉ。それはまた。随分と“不穏な逸材”じゃないか・・・。
ふーん、神官、ね・・・。南地は男女ともに見境がないんだよねぇ・・・。
・・・純潔主義が、聞いて呆れるとは思わないかい?」
(※にやにやしているヌル)
軍幹部の男「・・・使えそうでしょうか?」
ヌル「あぁ、実に最高だね。引き続き彼の身辺を洗い出せ。
“冥脈の女神”を我が忠犬に変えられるかもしれない好機だ。
結果によっては、君は相当な出世を果たすことになるだろう。期待しているよ?」
軍幹部の男「・・・! ありがとうございます・・・!」
▼後日――。
― 母親は「冥脈の女神の神殿」の偉人。
― 父親は「南地豪族(ブレイズ家以外の一大勢力)」
この話はこれをネタに北地との密約が交わされて、
実質北地がセントラルの配下に入った後。
軍幹部の男「ヌル将軍、お連れしました。さぁ、オッド、御挨拶して。」
オッド(推定4)「・・・・・・。」
軍幹部の男「ぐずぐずするな!!大将閣下の御前であるぞ!!」
ヌル「いいよ、二人とも楽にして。」
軍幹部の男「大変申し訳ありません。今後厳しく躾けます故・・・。
して、大将閣下・・・、わたくしの特進に関しましては・・・」
ヌル「あぁ、その話はあと。ちょっと黙ってて? 先に本題だ。
さて、オッド・メドロア君と言ったかな?
今日はセントラルの盟主、まぁ、要は皇族のとある御方から君に“お誘い”がかかってね。
君の今後に関わるとても大事な話だ。聞いてくれるかい?」
オッド「・・・お誘い? 僕、もう先生のところに帰りたい・・・。」 (※養護施設の人のこと)
軍幹部の男「おまえの父親はこの私だと、何度言ったらわかるんだ・・・!」 (※THE 虐待)
オッド「痛い・・・!ごめんなさい・・・!」
軍幹部の男「まったく・・・スラム街で育っているだけあって本当に反抗的な子でして・・・
これは部隊編入までには相当な時間を要す・・・うがっ・・・!
な・・・なぜ・・・だ・・・・・・、誰・・・か・・・医者を・・・」
(※胸に突き刺さるヌルの長刀)
ヌル「黙ってろ、と言ったはずだが? 同じ事を何度も言わせないでほしいものだね。」
軍幹部の男「こ・・・この・・・悪魔め・・・・・・貴様など、わたしが昇進さえすれ・・・ば・・・・・・」
(※事切れる。どんまい雑魚キャラ。)
ヌル「出世おめでとう、准将殿。二階級特進。これで君は晴れて中将に昇格だ。
あ、それでも私の下か。野望は遠いねぇ。・・・って、もう聞こえてないか。」
オッド「あ・・・。」(※割と落ち着いた様子で、困ったように事切れた元養父を眺めているオッド)
ヌル「おや、案外落ち着いているね。これは逸材だ。」
オッド「・・・どんな人でも、殺すのは、あまりよくないと思います。」(※少し悲しそうなオッド)
ヌル「・・・? あははははは・・・!
いやぁ、まいった。これは一本取られたね。気を悪くしたならすまなかった。
君のような子供にまさか倫理を諭される日が来ようとはね。」
オッド「・・・僕のことも、殺すんですか?」
ヌル「いや、まさか?言っただろう。お誘いがある、と。
単刀直入に言おう。君、軍属になる気はないかい?」
オッド「・・・戦うのは、もう嫌だ。」
ヌル「おっと。これは手厳しい。では、そうだね。軍医を目指す、というのはどうだい?」
オッド「・・・ぐん・・・い?って何?」
ヌル「あぁ、“お医者さん”だよ。軍専属のね。」
▼ODD:EP7-2(2073年~2075年):『神童時代①:軍医見習い』
オッド「・・・大丈夫ですか。すぐに楽になりますからね。」
軍人「・・・ありがとう。君は命の恩人だ。」
軍医「いやぁ、助かるよ。君、ヌル将軍のお墨付きなんだって?
まだ士官学校生というから大丈夫かと心配していたんだが、杞憂だったね。
冥脈神殿の神官と同じ高位回復魔術が扱えるなんて。もしかしてあちらの出身かい?」
オッド「そうかもしれません。わからないんです。僕、孤児なので。」
軍医「・・・そうか。それはつらいことを聞いた。すまないね。引き続き、頼むよ。」
オッド「大丈夫です。こうして人の役に立てる今が僕は幸せですから。頑張ります。」
(※少し悲しそうなオッド)
オッド「・・・戦争なんて、早く終わればいいのに。」
▼ODD:EP7-3(2075年):『神童時代②:戦争終結』
オッド(推定7)「・・・終わったんだ、ほんとに。」
▼ODD:EP7-4(2079年/推定11歳):『神童時代③:士官学校卒業』
士官学校の友達「飛び級で卒業かよ。いざとなれば前線にも出れるわけだろ?
まじですげぇよオッド。よっ、期待の逸材!頑張れよな!」
オッド「あはは。でも、もう前線に行く必要はないでしょ。
戦争は、終わったんだ。」
士官学校の友達「それもそうだな。アダム・ブレイズにはほんと、感謝だな。」
オッド「うん、そうだね。」
▼ODD:EP7-5(2083年/推定15歳):『政府方針転換:人類魔法使用制限』
軍人1「オッドのやつ、例の“制限装置”のお世話になるらしいぜ?」
軍人2「まじかよ。笑える。一気に“障害者”じゃん。」
軍人3「ほんとに制限量内に収められるようになるんかねぇ?」
軍人4「できなかったら退役だろ。出世コース絶たれたよなぁ。ざまぁ。」
オッド「・・・頑張らなくちゃ。」
▼ODD:EP7-6(2085年/推定17歳):『アベルとの出逢い』
アベル(12)「いってぇ・・・。あいつら、やりたい放題やってくれやがって・・・。」
オッド(推定17)「君が、砂漠から来たっていう・・・例の・・・」」(※オッドは軍医:手当て中)
アベル「何だよ、おまえも何か文句あんのか?!」
オッド「いや、そうじゃなくて・・・。魔法使えないのに、三人相手に勝っちゃったの?
すごいね・・・剣豪・・・?」
アベル「・・・なんだよぉぉ、話のわかるやつもいるじゃねぇかぁぁぁぁ!
そうなんだよ!ちゃんと試験受かったのにさ。不正疑われてもうあったまきてさ!!」
オッド「あぁ・・・それでこの喧嘩、ってわけね。
まぁ、そういうことなら報告書にはそう書いておくけど、
僕も君とは違う意味で“厄介者”だから、その、あんまお役には立てないかも。ごめん。」
アベル「・・・それ、制限装置?そっか、おまえも苦労してんだな・・・。
よし、今日から俺らは友達だ・・・!俺はアベル・アーセス!よろしくな!えっと・・・」
オッド「オッド。オッド・メドロアだ。」
▼ODD:EP7-7(2090年/推定22歳):『北地転属』
▼前日譚
オッド(推定22)「え?北地へ転勤・・・ですか・・・?」
ヌル「そ。」
オッド「・・・・・・やっぱり、僕がセントラルに居るとやりづらいですよね。
すみません、ヌルさん・・・。今まで本当に、ありがとうございました。」
ヌル「え? あぁ、違う違う。左遷じゃないから安心したまえ。」
オッド「・・・? いや、でも、北地・・・ですよね・・・?」
ヌル「うん。もう転属手続きはしといたから。はい、これ。」(※転属地等が書かれた書類)
オッド「え?ちょ・・・待ってくださいよ?せめてもう少し説明・・・」
(※ひらひら、と手を振って立ち去ってしまうヌル。)
▼本編
僕は今、旅行用のキャリーケースを一つ引いて、北の大地に立っている。
あまりにも急な転属命令だったので、必要最低限のものを慌ただしく詰め込んできた形だ。
僕とルームメイトだった友人のアベルが、後々必要なものは送ってくれる手筈になっている。
オッド「さっむ・・・。」
まだ10月の、しかも昼だというのに、辺りは一面の銀世界だ。
オッド「これは早々に上着を新調しないと厳しそうだ・・・。」
とりあえずは“新しい勤務先”とやらに出向いて、今後、僕の上官となる方へ挨拶をするのが本日の任務だ。ちなみにヌル将軍からもらった書類にはその“上官の名前”が記載されていない。
オッド「書類不備だよなぁ・・・。適当すぎるんだよね、将軍は昔から・・・。
一応ちゃんと軍の施設・・・っぽいけど・・・。
えっと・・・、軍事特務機関、“フォルスダッドコール”・・・?」
「聞いた事ないんだよな・・・?」とオッドは入口の看板の文字を読みながら首を傾げる。
ここはセントラル領内の北地国境哨戒塔の真北にあたる。
あちらと同じくかなり物々しい警備体制が敷かれてはいるのだが、にしては、哨戒塔があるわけでもなく、なんならごく普通の人民居住区を彷彿とさせる“家”以外の何者でもない建物さえ見え隠れしている始末だ。
オッド「・・・・・・末端には知らされていない施設、だよな・・・明らかに・・・。
闇医者にでもなれ、ってことか・・・?」
僕が“魔素喰らい”と呼ばれる厄介者となってからも、幼い頃に“書類上の後見人”、まぁ、つまりこの孤児の保護者となってくれたヌル将軍は退役を進めてきたりはしなかった。
それどころか、アベルに巻き込まれる形で彼女と再会した後は、“将軍直属の特別部隊”へと僕を無理やり転属させる形で、なんだかんだ、周囲からの不遇な扱いを改善してくれた人だった。
要は、彼女のおかげで僕はこれまで軍医を続けてこられている。
オッド「・・・信じてみるか。」
幼い頃、彼女は数日だけ養父となった軍人の男性を、僕の目の前で切り捨てたりもしたけども。
オッド「あれも、子供が殴られてるのを助けてくれただけだしな・・・。
道理は通す人だから、きっと今回も何か理由があるはず。」
自殺の名所、テルミナの森のすぐ傍の不気味な施設ではあるけれど、きっと大丈夫だ、と気を取り直すと、僕は入館証を受付の警備の人に提示して、背筋を伸ばしてその建物へと入っていくのだった。
▼
オッド「あの~・・・。」
将軍にもらった1枚の書類に記載されてあった『魔導宝飾開発研究課』とやらをようやく探し当てて、その入口の扉を恐る恐る開けた僕は、異様な雰囲気に飲まれてドアの隙間から中を覗き込む形でオフィスへ入ることを躊躇している最中だ。
軍の施設だというから、軍服の人がたくさんいるかと思っていたのが、ここまで出逢った人達も、ここから見えている人達も、みんな“明らかに軍人の様相ではない”。
白衣をまとって目の下にクマを携えた、不健康そうな人の何と多いことか・・・。
オッド「・・・研究員さん、ってことで、いいんだよな・・・?」
研究員「ん?君、どうしたの?」
思わず独り言をつぶやき始めていた僕に気付いて、入口近くの机で目の上に疲労回復用のシートを乗せて天を仰いでいた職員さんが話しかけてくれている。助かった。
オッド「あ、えっと、今日からこちらに配属されたオッド・メドロアと申します。
とりあえずこちらの部署へ・・・という指示なので伺った次第なのですが・・・」
研究員「えぇ?そんな話朝礼ではなかったけどなぁ。
“課長”ならあの部屋にいるから行って確認してみれば?」
オッド「承知しました。ありがとうございます。」
目の前ですっと指差された部屋の最奥の扉に向かって意気揚々と歩きだそうとした僕を、その研究員さんがおもむろに呼び止める。
研究員「あー、待って。僕からのアドバイスだ。
“課長”が作業に集中してたら、声をかけるのは後にした方がいいよ。」
オッド「え・・・。そうは言われましても、どなたかに指示を頂きませんことには・・・。
こちら、大将閣下からの上官命令でして・・・。」
書類には『“彼”の指示に従って本日中に早急に勤務に当たるように』と、とても短く、ヌル将軍からの言付けが記載されている。
研究員「まぁ、そういうことなら止めないよ。健闘を祈る。」
オッド「ご心配、ありがとうございます・・・?」
気難しい、ということだろうか。まぁ、そうならそうで仕方ない。
何と言われようが、僕はこれでも軍人の端くれで、上官命令は絶対だ。
意を決して指定された扉へ向かい、そしてしっかりとノックをする。
が、対応してくれた研究員の彼のいうとおり、まず返事がない。
仕方ない・・・、とそーっとその扉を開けてみると、そこにはひとつ広い机が置かれていて。
それに向かう、これまた翠の目の下に不健康そうなクマを携えた細身の男性が、こちらにはまったく気づく様子すらなく、何かを作ることに集中している様子が伺えた。
オッド「し…失礼します…。」
そのまま部屋の主の許可なく入室して扉を閉めるが、その音にも気づいていないようなので、僕は、疲れた様子ではあるもののかなり端正な顔立ちが美しい“課長”へと歩み寄って、その肩を軽く叩いた。
課長「うわ、びっくりした!? 危ない、と何度言ったらわかるんだ…!
精密な機械なんだから、確認なら後にしてくれ!…なぃ……って、君、誰だい?」
オッド「お…お取込み中すみません…。
あの…、本日付けでこちらへ転属となりました。オッド・メドロアと申します。
ヌル大将閣下より“魔導宝飾開発研究課”の方から指示を仰ぐように、
…とだけ申しつけられておりまして…
その…書類には、こちらの上官のお名前すら記載されていないもので……
私はこの後どうすれば…」
課長「……。」
事情を説明しながら、ここの“課長”らしき目の前の男性へ、将軍からもらった1枚の書類を渡すと、彼はそれにさっと目を通して、そして盛大にため息をついて机に伏してしまった。
オッド「(面倒、ということだろうか…これは困ったな…)」
課長「何一つ説明されていないみたいだね…。」
終始上品な物腰の方ではあるのだが、声色は明らかに怒っている。
これは転属早々怒鳴られることになるかもしれないな、と覚悟を決めた僕だったが…
課長「どうしてあの人は、こう…、いつも、いつも……
明らかに面白がっているとしか…。
私は君には十分な準備期間を与えて出発させてくれ…と言ったはずなんだが…。」
オッド「え、じゃあ、そちらの書類の“彼”とは、貴方のこと、ということで…」
課長「そうだ。すまなかったね。まさか翌日に派遣されてくるとは…。大変だっただろう。」
オッド「…あはは。慣れてますので…。」
どうやら彼が怒りを向けているのは、僕ではなく、将軍、ということのようで、僕は内心安堵
に包まれながら彼へと話を続ける。
オッド「それで、僕はこの後どうしましたら…」
課長「ちょっとね…まさか昨日の今日でこうなるとは思っていなかったから…
何も準備してないんだ。
すまないけど、この仕事が片付くまで待っていてくれないかい?
締切がね…、意地でも守らないとリリス…
あぁ、えっと、ここの所長に私の部下もろとも氷漬けにされてしまう次第で…」
オッド「……。そんなに怖いんですか?」
課長「あぁ。絶対に、怒らせたくない…。絶対にだ。」
死んだ魚のような目で作業を再開し始めた端正な顔立ちの彼の物言いに、僕は少しばかりの同情を覚えてしまっていた。
オッド「……しょ、承知しました。では、私もお手伝いを…。
皆さんお疲れのようですので…給湯室はどちらでしょうか?
お飲み物、用意してきます。」
課長「ほんとかい?それは助かるよ。給湯室は2階にある。私はコーヒーがいいな。
部下たちには紅茶3つと、コーヒー5つ、ダイエット中の子が1人いるから、
彼女には白湯を。」
オッド「え、あ、はい。わかりました。行ってきますね。」
課長「ありがとう。急がなくていいからね。」
全員の好みを把握しているのか、と僕は驚きを覚えながら、彼の部屋をあとにする。
オッド「いい上司みたいでよかった。…あ。名前聞き忘れたや。」
「ま、いっか、あとで。忙しそうだし。」と普段からあまり細かいことを気にしない僕は、問題が解決した嬉しさもあり、軽い足取りで教えられた給湯室へ向かうのだった。
▼
課長「オッド君、起きてくれ。終わったよ。」
オッド「…え?あれ。すみません、僕、いつのまにか…」
皆さんへと飲み物を配り終わった後、僕はやることがなくなってしまったのだが、気を使ってくれたであろう“課長”が再び彼の部屋へと僕を招き入れて、あろうことか彼の個人所有のノートパソコンとヘッドフォンを貸してくれたものだから、「一応勤務時間なんだけど、いいのかなぁ…」と若干罪悪感に苛まれながらも、まるで休暇中のように見たかった映画の鑑賞を楽しみ始めたところまでは覚えている。
課長「昨日の今日での北地への強行軍だ。疲れていたんだろう。よく眠れたかい?」
いつのまにやら毛布までかぶせてくれていたようで、それはもうスッキリとした気分で目覚めてしまった僕は、目の前で非常に疲れた顔をしている締切明けの上官に、ものすごい罪悪感を感じながら、精一杯の謝辞を述べるしかなくなってしまった。
オッド「お…お心遣い、痛み入ります。なんか…すみません、ほんと。」
時刻を見れば、夜9時を回っている。ということは、彼は完全に残業だ。
オッド「その…なんというか…大変ブラックな職場なようで……」
課長「あはは…。人手がね、足りてないんだ。さ、今日のところは帰ろうか。」
オッド「…あ。僕、そういえば軍寮の手続きとかも…何も聞いてないんですけど…
もう受付閉まってますよね…。ど、どうしよう。」
課長「あぁ、大丈夫だよ。君の家ならもう決まっているから。ついてきて。」
オッド「あ、そうなんですか?よかった…」
いやに手際がいい上司にさらに感謝しながら、僕は彼のあとへとついていく。
建物から出て、少し歩くとここへ来た時に見えていた“居住区”らしき場所へたどり着いて、そして僕は彼に言われるがままに案内された立派な家へと足を踏み入れた。
課長「ただいま。」
女性「あら、おかえりなさい。ずいぶん遅かったのね。」
課長「だいたいは君のせいだろう…。“リリス”。」
リリス(29)「まぁ、人聞きの悪い。これでもだいぶ折れたつもりなのだけど…?」
リリスと呼ばれた可愛らしい顔をした女性が、頬に手を当ててにこにこと笑っている。
彼の奥さんだろうか。美男美女で大変目の保養になるご夫婦だ。
リリス「あら、そちらはどなた?」
オッド「あ、初めまして。本日付けでこちらに転属になりました。
オッド・メドロアと申します。」
課長「例の軍医さんだよ。」
リリス「…まぁ。まぁまぁ。あなたがヌルさまの…!それは歓迎しなくちゃね。」
課長「あぁ、彼、昼から何も食べてないんだ。夕飯を用意してやってくれないか。」
リリス「はーい。オッドさん、あなた、ビーフシチューはお好きかしら?」
オッド「は、はい。大好物です。」
リリス「それはよかった。多めに作っておいてよかったわ。ちょっと待っててね。」
そう言うと、彼女はパタパタと足音を鳴らして、奥のキッチンへと走っていく。
課長「さ、あがってくれ。」
オッド「あ、あの…今日は泊めて頂ける、ということでよろしいんでしょうか?」
課長「ん? あぁ、君の家は今日からここ、なんなら勤務地もほとんどはここだから。」
オッド「…はい?」
課長「ヌルが何にも話してないみたいだから、どこから話そうかと思ってたんだけど、
何にせよ、まずは名乗らなきゃいけないね。」
オッド「…あ、そういえばまだお名前伺ってませんでしたね。」
アダム(30)「僕の名前はアダム・マイヤ。旧姓は、ブレイズだ。改めてよろしくね、オッド君。」
オッド「…え? 何の冗談でしょうか…?」
この人、冗談もいうのか…と僕が心底不思議そうな顔を浮かべていると、
アダム「あはは…まぁ、そうなるよね…。残念ながら冗談ではなくて…だね…。」
彼は困ったようにそう言って苦笑いしていて…。
そうだ…、これは仮にもあの将軍からの命令で……かの英雄を北地に飛ばした…とアベルがさんざん将軍に対して文句を言っていたのも思い出されて…、とだんだん頭の中で状況が繋がっていってしまい…。
オッド「………………え?? ほんとに、“救国の、英雄”…?」
アダム「久しぶりに聞いたなぁ、それ。ずいぶん昔の話だよ。
今はほら、ご存じのとおり、ただの研究職だから。」
「軍人ですらない、一般人だよ」と付け加えてキッチンの方へそそくさと歩いていく彼を慌てて追いかけながらも、僕は目の前の“有名人”の正体をこの時、まだ受け入れきれずにいたのだった。
▼
リリス「お口に合うといいんだけど…」
オッド「いや、美味しいです。ほんと。」
リリス「あらぁ、ほんと? よかったぁ。」
僕は今、あのリリス・マイヤ卿に手料理を振舞われて、あのアダム・ブレイズと一緒に食卓を囲っている。
アダム「イヴは?もう寝ちゃった?」
リリス「えぇ、ぐっすり。」
アダム「…はぁ。このままでは忘れられてしまうよ…。」
リリス「そうねぇ。たしかに、もはやリリンの方が親らしいまであるわねぇ。」
アダム「…僕はイヴにとって“カガリビト”以下ってことかい…?
もうこの際、辞職でもしようかな…。」
リリス「あら、それはだめ。受け付けませんからね。」
アダム「…はぁ。君はそういう人だよね…。」
リリス「あらぁ、そうだとわかってて結婚したんでしょう?」
この状況は、いったい何なんだろう…。とりあえずリリス卿の手料理は非常に美味いし、家の中はとても暖かいし、今のところ特に不満はないけれども、明らかにこうなるとわかっていてわざとアダム・ブレイズの名を記載しなかったであろう上官の顔を思い出して、僕はとても複雑な心境のまま、仲睦まじい夫婦の他愛もない会話を眺めるだけの人になってしまっている。
たしかにこれは「左遷」ではなさそうだけれど…
オッド「(意味が分からないです、ヌルさん。)」
▼
オッド「はぁ、美味しかった…こんなまともな飯食べたの久しぶりです。」
アダム「そうか、それはよかった。
さて、腹も満ちたところで、そろそろ本題だ。
明日からのオッド君の仕事についてなんだけど…」
リリンと呼ばれたおそらく最新型の“カガリビト”が手際よく僕たちの食べ終わった食器を下げていくのを「すごいな…さすが発明者直々の最新型…」などと呟きながら興味深そうに眺めていた僕に、目の前の“英雄”が話を切り出す。
オッド「あ、はい。助かります。
今日はさぼって映画見て寝ているだけの人にしまったので取り返さないと…」
リリス「…あらぁ、そこからなの?」
アダム「ヌルのいつものお戯れだよ。
これ1枚持たせて昨日の今日で職場の方に彼を派遣してきたんだ…」
アダムさんから例の不備だらけの書類を受け取って目を通したリリス卿はというと、いったん目を丸くした後、盛大に笑いを漏らしている。
リリス「ヌルさまらしいわね。」
アダム「勘弁してほしいよ、毎度毎度…。
というわけで、ヌルのかわりに僕が説明するんだけど、さっきも言ったとおり、君の明日からの勤務地はここになる。
僕の娘…、イヴの“主治医”として彼女の面倒を見てほしいんだ。」
オッド「娘さんの、主治医…ですか? 僕が…?」
「まだ若輩者ですが…」と続けて、僕は目を丸くする。それもそのはずだ。なんたってここはあの救国の英雄と、世界にシンギュラリティをもたらした偉大な科学者の“家”、というには少々立派すぎるお屋敷なのだから。軍にはもっとベテランの医師たちがたくさんいるわけで、なぜ、そういった方々の下について働いていただけの未熟者にそんな大役が回ってきたのか、あまりにも解せない。
アダム「君の経歴を見せてもらったよ。
“魔素喰らい”の神童…とヌルが言っていたけど。」
オッド「あ…。はい…。そちらについても把握済でしたか。
でしたら尚更、どうして僕のようなものにそのような大任を…?」
少しばつが悪そうに頭をかいて、僕は英雄に問う。
アダム「…苦労したんだね。あまり自分を卑下するのはよくない。
経歴から見ても、君は申し分なく仕事をこなしてきているのだから。
胸を張るといい。」
オッド「……。あの救国の英雄から、そのような激励を頂ける日が来るなんて、生きているといいこともありますね、ほんと…。」
嬉しかった。いつも周囲の“カガリビト”へ影響を出さないように細心の注意を払って仕事をしてきた数年だったわけで、僕が魔法を使うと周囲の人間は皆一様に心配そうな目でこちらを見るものだから、ずっと肩身が狭かったのは事実だ。正直、彼にも開口一番「気を付けてくれ」と注意されると思っていたのだが、まさかの労いを頂いて、もう立派な大人だというのに少し涙をこらえるのに苦労している。
アダム「で、物は相談なんだけれどね。君にはその特殊な経歴から来る経験や知識を、ここで遺憾なく活かしてもらいたい。」
オッド「…と、いうと?」
アダム「…娘もね、“魔素喰らい”なんだ。おそらく、君以上にね。」
オッド「…!」
少し悲しそうに事情を話す英雄の話に驚きはしたが、同時にすぐに合点が行った。そういうことなら、たしかに僕にお呼びがかかった理由も頷ける。
アダム「彼女は今、5歳になる。今までは屋敷の中だけで満足してくれていたのだけどね。
最近、外の世界に興味を示し始めたものだから…その…」
オッド「もしかして、制限装置、何度も壊れちゃってますか?」
アダム「あはは…お見通しだね。そうなんだ。
ちょっと職権乱用になってしまってるので内密にお願いしたいんだけど、、
軍用と同じパーツを使った、僕直々のお手製なんだけどね。
それこそ、君が今つけてるのよりもだいぶ強力な代物だ。」
オッド「…ぇ。それは…。」
話を聞いて、僕の頭には二つの心配が同時並行的によぎっていく。
コストの問題…は…まぁ、腐っても救国の英雄と稀代の科学者のおふたりなので大丈夫なのかもしれない…が、これより強力な魔素制限を…わずか5歳の女の子に…?
オッド「…娘さん、えっとイヴさんの体調は今、どういった具合でしょうか?」
アダム「…やはり、話が速いね。実は、あまり芳しくないんだ。」
リリス「そうなのぉ。もう可哀想で、可哀想で…。今日もしっかり発熱中よ。
最近ずっとこんな調子で、私思わず制限装置をちょっといじってしまってね…」
「出力を緩めたんだけど…」と続ける母親の顔をした可愛らしい女性の一言に、僕はその後の想像がついてしまって…
オッド「あぁ…、もしかして…今リリンさんしかここにいないのは…」
リリス「そういうこと。他の子は全部故障しちゃって、今ラボで私の部下が調整中。
この子は最新型だから、何とか生き残ってくれたのだけど…」(※部下=ノア)
リリン「おかげで仕事が回っておりません。早急に何とかして頂きたい次第でございます。」
オッド「だからリリス卿がお食事の準備をしてらしたんですね…。」
リリス「そっ。今日は全てのお仕事をアダムに任せて、リリンのお手伝いをしていたの。
まぁ、お料理は好きだから全然いいのだけれど。
ただ、私もアダムもお仕事が忙しいから、ずっとこのままというわけにはいかなくて…」
オッド「なるほど。それで僕をイヴさんの世話役に、ということでしょうか。」
リリス「ええ、そうなの。私からヌルさまに有給消化のご相談をさせて頂いたら
“これ以上ない適任を知っている”ってはしゃぎだしちゃったのが昨日の朝のことよ。
栄誉あるセントラル勤務の軍人さんにこんな僻地にお越し頂くには、それなりの時間がかかると思っていたのだけど、まさか1日で来て頂けるなんて。」
「ヌルさまは本当に仕事が早くて助かるわ!」と続けて、満足げに微笑む彼女に、遠慮、といった機微はまったく感じられない。横で非常に申し訳なさそうな顔をしている、先ほどまで彼女の仕事の全てを肩代わりする形で残業していたであろう英雄の、ここまでの苦労が少し垣間見えて、僕は思わず苦笑いを漏らしていた。
オッド「あはははは…。」
アダム「…と、いうわけなんだけど、引き受けてもらえるかい?
本当は僕がずっとついててやりたいんだけど、
このとおり、鬼の上官たちが休ませてくれないものでね。」
リリス「あら、人聞きの悪い。
だってどちらかが休まなきゃいけないのなら私の方が適任でしょう?」
アダム「それは、そうなんだけど…。」
「僕だってイヴと休暇を過ごしたい…」と哀愁漂った様子でうなだれる英雄の姿がそこにはあって、人間らしく落ち込む“彼”に、僕は畏れ多くも親近感を感じていた。
オッド「承知しました。僕なんかでよろしければ精一杯任務に当たらせていただきます。」
アダム「…! 助かるよ。急な申し出だったのに、本当にすまないね。
どうか、イヴをよろしく頼む。」
イヴ(5)「ママぁぁ…リリ~ン……喉が渇いたぁ…。」
勢いよく返事をしようとしたところで、小さな女の子の声が聞こえて、僕はドアの方へと視線を移す。可愛らしい金髪の女の子が眠そうな目をこすりながらリリス卿の元へと歩いてきて、そのまま彼女に抱きついている。少し顔が赤い。熱が高いのだろう。
リリス「あらあら、起きちゃったの? リリン、何があるかしら。」
リリン「マスター、イヴ。おはようございます。
りんごジュースとお紅茶、お水やミルクもございますが、いかがなさいましょうか?」
イヴ「ミルク…!あったかいのがいい!」
リリン「承知いたしました。ご用意いたします。少々お待ちください。」
イヴ「わーい、ありがとリリン~。」
アダム「イヴ……。た、ただいま。」
イヴ「……? あ、パパだ。おうちに居るの、久しぶりだね…!」
アダム「うっ…。す…すまない。お仕事が忙しくてね…。」
相変わらずリリス卿に引っ付いたまま、あどけない少女が笑顔で発した実に悪気の無い一言に、あの救国の英雄がいたくへこんでいる。おそらく今すぐ抱きしめに駆け寄りたいが、空気を読んで我慢している、といった雰囲気だ。あまりにも寂しそうなので、思わず僕はリリス卿と顔を見合わせて、苦笑いを交わしてしまう。彼女が少女へこそこそと耳打ちをすると、ぱっと目を輝かせた少女はリリス卿へと頷いた後、大好きな母親から離れて、しょぼくれている英雄の方へ向かって歩いていく。
イヴ「パパぁ~、お仕事お疲れさまぁ~。」
アダム「…! イヴ…おいで。」
先ほどまでの様子とは打って変わって、非常に嬉しそうな様子で少女に向かって両手を差し出した彼に向かって、金髪の少女がダイブする。まるで繊細な壊れものでも扱うかのように優しく彼に抱きしめられた少女は、とても満足げな様子で、そんな父親に向かって可愛らしい笑みを返していて、僕はその光景を心地よくも、不思議な気持ちで眺めていた。自分は孤児だから、親の愛情というものを受けたことは一度もない。知らない感情だ。だけど…
オッド「(こんなにも…温かい気持ちになるものなんだな。)」
なんだか、素敵なものを見せてもらったようで、少し感動してしまっていた僕に、英雄の膝の上で落ち着いた少女が話しかけてくる。
イヴ「おにいちゃん、だぁれぇ~? 新しい“カガリビト”さん?」
オッド「え、いや、僕は…」
そ…そんなに機械っぽく見えるだろうか…?
突拍子もない小さな子供の質問に僕が困っていると、
アダム「このお兄さんは“人”だよ。イヴ。」
英雄が慣れた様子で彼女の質問に代わりに答えてくれている。
イヴ「なぁんだぁ。イヴのせいで動けなくなっちゃった子たちの代わりかと思っちゃった。
ねぇ、パパ、みんないつ帰ってくる? ほんとに、ちゃんとみんな直る?」
アダム「今、ノアお姉さんが頑張ってるよ。
……おそらく、寝る暇も惜しんで。」
後半は明らかに失笑交じりの独りごとだった。
おそらく“残業”の被害を被ってる人が彼の他にもいるんだろう。
イヴ「そっか!ノアお姉ちゃんならきっと直してくれるね…!よかった!
みんなが帰ってきたら、イヴちゃんと謝らなきゃ。」
アダム「そうだね。でも、みんな怒ってないよ。そんな心配しなくても、大丈夫だ。」
イヴ「そうかなぁ…。だって、絶対痛かったはずだもん…。仲直り、できるかなぁ…。」
実に子供らしい発想だ。父親に頭をなでられて励まされている小さな少女は、“カガリビト”を人と同列に扱って、おそらく彼女が魔法を発動した際に彼らの動力へ干渉してしまったが故の“機械の故障”に心を痛めて、そして、今後の彼らと自分との関係を気にしているようだった。
機巧人形への“疑似精神”の搭載が主流になってからというもの、彼らが人のような豊かな感情表現を見せるが故の弊害のひとつだろう。その動きが全てプログラムされたものだというのは、年端も行かぬ少女にはまだ理解できないようだった。
アダム「それでね、イヴ。パパ、明日もお仕事だから、“お医者さん”に来てもらったんだ。
このお兄ちゃんが、明日からイヴの面倒を見てくれるよ。さぁ、ご挨拶して。」
イヴ「…お医者さん? お兄ちゃんはノアお姉ちゃんとおんなじ?」
「じゃあ、みんなも直せる?」と期待の目を向けられて、僕はなんだか申し訳ない気分で返答に困ってしまう。
オッド「あ、えっと…」
アダム「あはは。お兄ちゃんは“人”専門のお医者さんだよ。
つまり、イヴだけのお医者さんだ。」
イヴ「そうなの? えへへ。えっと、よろしくおねがいします!
おにいちゃん、お名前は?」
オッド「オッド。オッド・メドロアっていいます。よろしくね、イヴちゃん。」
イヴ「オッド…かっこいいお名前だね!オッド先生って呼んでいい?」
オッド「うん、いいよ~。まずはお熱を下げないとね。」
アダム「みんなと競争だな、イヴ。先生の言うことを聞いて、ちゃんと良い子にするんだよ。
みんなより早く治せたらパパがご褒美をあげよう。」
リリス「あら、それは私も頑張らなくちゃね。負けられないわ。」
イヴ「えぇ…。ママが本気で頑張ったら、きっとイヴ、みんなに勝てないよぉ。」
リリス「ふふふ…、負けた方が罰ゲームよ?そうね、お野菜食べるとかどうかしら?」
イヴ「うっ…。ニンジンは嫌ぁ…。オッド先生…!早くイヴのこと治して!」
「イヴが負けたらオッド先生も道連れなんだからね!」と焦った様子の少女に言われて、「いや、僕はニンジン大好きなんだけどな…」などと若干困惑しながら、
オッド「が、頑張るよ…。」
彼女にどうにも自信のない返事を返すと、それでも少女は天使のような顔で笑って、
イヴ「よーし!絶対勝つぞぉ!ねっ、パパ!えぃ、えぃ」
アダム&イヴ「「おー!」」
英雄とともに可愛い気合を入れ始めるものだから、
オッド「お…おぉ~?」
思わずつられて彼らの掛け声に合わせながら、僕も小さく右手をあげるのだった。
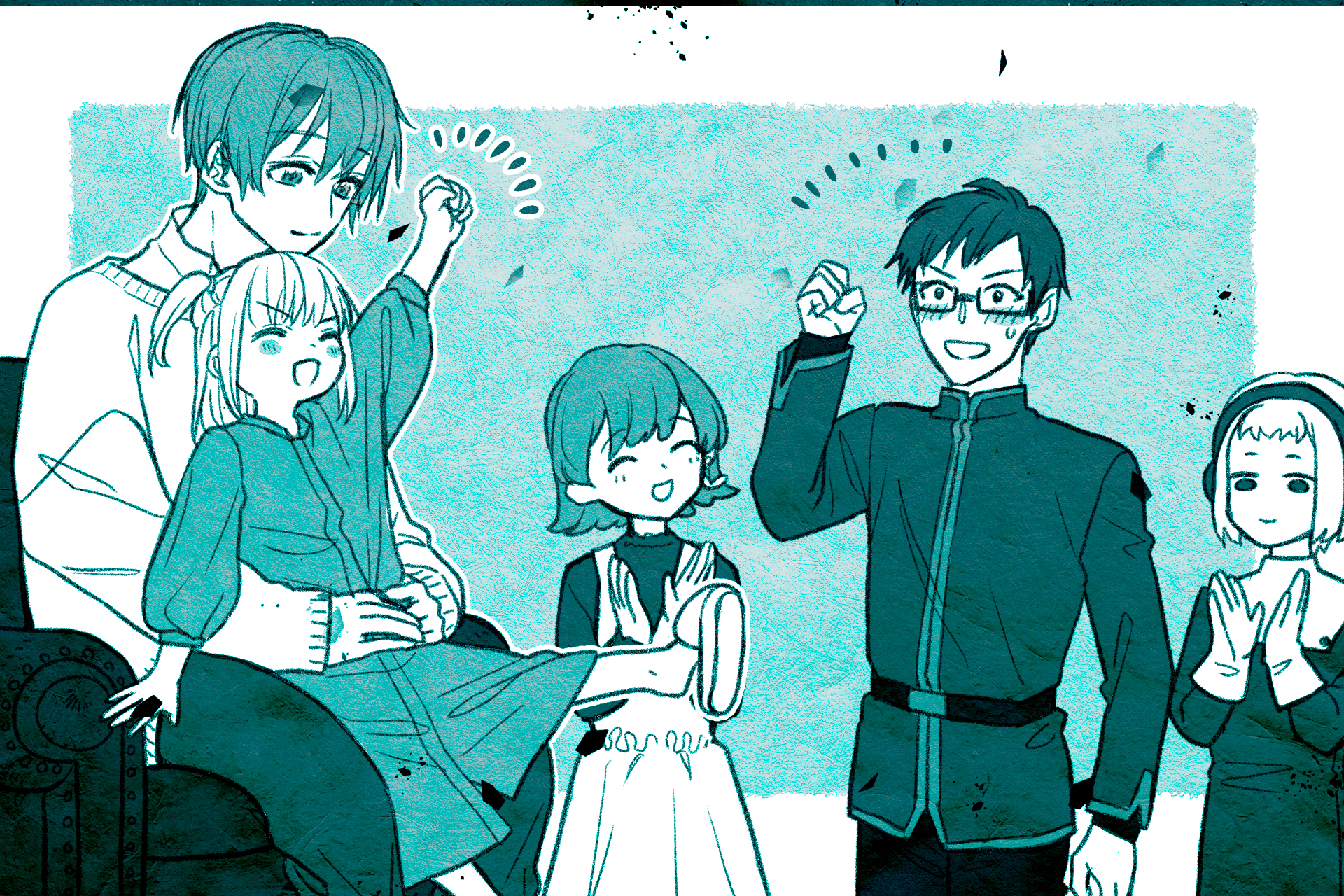
こうして僕は若くしてセントラルを離れる形で、救国の英雄のお屋敷にお世話になることになったのだった。守秘義務があるので急な転属を左遷と認識して何度も励ましの連絡をくれたアベルにもこの任務の詳細は話せず、「まさか英雄の家にお世話になってるなんて、ばれたら暫く恨まれそうだ…」と、彼と話すたびに僕は微妙に申し訳ない気分を味わうことになる。
ちなみにあの日の後、僕に与えられたお屋敷の隅の一室は、セントラルでアベルとシェアしていた軍寮なんか目じゃないほどに広くて、しかも、どこまでも気遣いの行き届く人の出来た救国の英雄の計らいで僕専属の“カガリビト”までつけてもらったものだから、「なんか…急にお貴族さまになったみたいだ…」と暫く絶妙に落ち着かなかったのはここだけの話である。
※ストーリーはキャラクター順に繋がっています。








